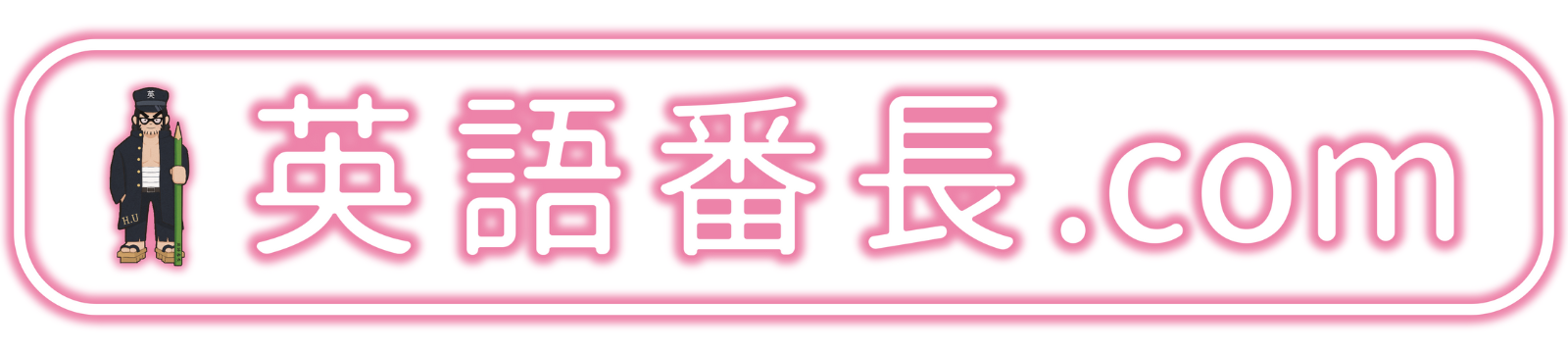seemは歴史的に非常に興味深いプロセスをたどっています。
今回は seem ができるまでの流れを見ていきます。
語源:「ふさわしい」から「見える」へ
seem は、古英語(OE)ではなく、古ノルド語(ON:バイキングの言葉)の sœma に由来します。
本来の意味: 「(〜に)ふさわしい (to befit)」「調和する」
変化: 「ふさわしい」→「(そのように)見える」へと意味が転じました。
この段階では、後の「seem like 〜」につながる「〜のようだ」という意味の基礎ができました。
非人称構文の時代(中英語期)
中英語期、seem は 「非人称構文(Impersonal Construction)」 でよく使われていました。
これは、現在の It seems to me that… の原型ですが、当時は It すら省略されることがありました。
Me semeth (that)… 「私には……のように思われる」
ここでのポイントは、「私(Me)」が主格(I)ではなく与格(〜に)であることです。
動詞 seem は、「出来事」を主語にして、「私」はその印象を受け取るだけの存在でした。
この「Me semeth」という塊は、文全体に対して「どうやら〜らしい」という判断を下す 副詞的なマーカー(文副詞)として機能していました。
「繰り上げ」による動詞への昇格
歴史の経過とともに、英語は「主語+動詞」の形を好むようになり、非人称構文が崩壊していきます。
非人称型: It seems [that he is honest].
「[彼が正直であること] が、思われる」
この It seems は、文全体の確信度を表す「副詞(It seems = Apparently)」に近い。
繰り上げ型: He seems [to be honest].
「彼は、正直であるように見える」
従属節の中にいた He が、文全体の主語の位置に「繰り上げ」られました。
この変化によって、seem は文の添え物(副詞的機能)から、主語と補語を結びつける主要な動詞(連結動詞/Copula) としての地位を確立しました。
まとめ
言語学者のエリザベス・トラウゴットなどは、seem のような動詞が「客観的な事実」から「話者の主観的な判断」を表す言葉へと変化した(主観化)と分析しています。
動詞への昇格: 本来は文全体にかかる「判断のラベル(副詞的な使い方)」だったものが、主語と結びついて He seems… という文の骨格を作る動詞へと役割を広げた。
副詞的側面: 現代でも He is honest, it seems.「彼は正直だ、どうやらね」のように、挿入句として副詞のように使われます。
seemは「文全体の意味を添えるだけの存在(判定詞)から、文の主語を支配する主要な動詞へと構造が変わった」興味深い動詞なのです。